投資信託に興味を持っているけれど、「やめたほうがいいのかな?」と不安に感じていませんか?
確かに、投資信託には元本保証がないことや手数料がかかるといったデメリットがあります。
しかし、少額から始められ、専門家に運用を任せられるといったメリットも多くあります。大切なのは、これらの特徴を理解し、自分の投資スタイルや目的に合った選択をすることです。
本記事では、投資信託を「やめたほうがいい」と言われる理由を具体的に解説しつつ、どんな人に向いているのか、どのように選べばリスクを抑えられるのかを詳しくお伝えします。
「投資信託は損をする?」
「手数料が高くて割に合わない?」
「ほかにもっと良い投資方法があるのでは?」
こうした疑問や不安をスッキリ解決できるよう、専門家の意見やデータを交えながら解説していきます。投資信託を始めるべきか悩んでいる方にとって、この記事が「自分でも投資が始められる!」と最適な判断をするためのヒントになれば幸いです。
投資信託をやめたほうがいい理由

まず、投資信託をやめたほうがいいと言われる理由について解説していきます。
元本割れのリスクがある
投資信託は短期間では元本割れのリスクがあるため、資金が減る不安を感じやすい人にはおすすめできません。
金融庁の調査によれば、国内外の株式や債券に分散投資していても、運用期間が5年以下の短期では元本割れする可能性があると報告されています。特に市場の下落局面では、基準価額が急激に下がることがあり、心理的な負担が大きくなりがちです。
2008年のリーマンショック時、多くの投資信託が短期間で基準価額を大きく下げ、一部の株式型投資信託では30%以上も元本割れが起こったケースがあります。想定外の暴落に耐えられず、投資をやめてしまった人も少なくありません。
短い期間で損失を出すリスクを避けたいなら、投資信託以外のより安全性の高い商品を選ぶことも検討しましょう。
運用手数料がかかる
投資信託には継続して運用手数料がかかり、その負担は長期投資になるほど大きく影響します。
金融庁の調査によると、国内の投資信託の信託報酬は年率0.5%~2.0%程度と幅があります。アクティブ型ファンドは1%を超えるケースも多く、運用が長期化すると最終的なリターンの差も大きくなりがちです。
例えば、年率1.5%の手数料の投資信託に100万円を20年運用すると、合計で数十万円単位の手数料を支払うことになり、最終的な利益は手数料が安いファンドよりも大幅に低くなる可能性があります。
手数料の負担をできるだけ抑えたい人は、運用コストが低い商品を選ぶか、そもそも手数料の発生しにくい方法を検討するのがおすすめです。
短期間での利益獲得が難しい
投資信託は短期間で大きな利益を求める人には向きません。
投資信託は基本的に長期運用を前提として設計されており、金融庁のデータでは5年以下の短期投資では資産が十分に成長しない可能性が高いと示されています。
2008年のリーマンショック時、短期で資金を投入していた投資家の多くは、数カ月の下落で元本を大きく割り込むという結果になりました。また、短い期間では市場変動の影響をまともに受けやすく、大きな利益を狙うのは難しいケースが多いのです。
「すぐに利益を出したい」というニーズが強い場合、投資信託はあまりおすすめできません。ハイリスクであっても短期トレードや別の選択肢を考えたほうがいいでしょう。
商品選択の難しさ
投資信託は本数が多く、最適な商品を選ぶのが難しいため、判断に自信がない方にはハードルが高いです。
日本だけでも6,000本を超える投資信託が存在すると言われています。金融庁の調査によると、投資信託の購入者の約半数が購入後の運用成績に満足していないという結果もあり、商品選びがうまくいっていないケースが多いようです。
銀行や証券会社で勧められるままに商品を買ったら、手数料が高かったりリスクが大きい投資信託を買ってしまい、想定外の損失を出してしまった人も少なくありません。
自分の投資目的やリスク許容度を踏まえて商品を選べない人は、投資信託ではなく、もっとシンプルな投資手法を選ぶか、専門家に相談するのも手です。
投資信託をやめたほうがいい人の特徴

つづいて、投資信託をやめたほうがいい人の特徴について、5つ紹介します。
短期間で大きな利益を求める人
短期的に大きな儲けを狙う人には、投資信託は不向きです。
金融庁のデータでも、投資信託は中長期の資産形成を狙う商品としての位置づけが強く、1年や2年といったスパンでの大幅なリターンは期待しにくい傾向が示されています。
リーマンショックやコロナショックの際、短期売買で利益を上げようとした投資家の多くが、暴落時に手痛い損失を抱えてしまいました。一方で長期保有していた人は、最終的には回復局面で利益を得ることができています。
「すぐに稼ぎたい」という方は、投資信託よりも短期トレードに向いた株式取引やFXなど別の手段を考えたほうが良いでしょう。
自分で銘柄を選びたい人
「自分でこの会社に投資したい!」と銘柄選択を楽しみたい人には、投資信託は不向きです。
投資信託はファンドマネージャーが複数の銘柄をまとめて運用する仕組みです。金融庁の調査でも「投資家の細かい意思を直接反映するのは難しい」というデータが出ています。
自分で個別株に投資している人は、特定の業界や企業を徹底的に調べ、買い時・売り時を判断して成果を上げる方もいます。一方、投資信託では組入銘柄を自分でコントロールすることはできません。
自分の投資センスをフルに活かしたい人は、投資信託ではなく直接株を購入するなど、自分で銘柄を選べる手段がベターです。
価格変動に敏感な人
値動きに一喜一憂してしまうタイプの人は、投資信託をやめておくほうが精神的に楽かもしれません。
投資信託も株式市場などの影響を受けるため、基準価額は日々変動します。金融庁の報告では、投資信託でも短期的には数%単位の上下が生じることは珍しくありません。
2020年のコロナショックで、基準価額が一時的に大幅下落。そこに耐えられずに解約した結果、後の回復局面で利益を取り損ねてしまった人がたくさんいました。
毎日の価格変動が気になって不安になるなら、無理して投資信託に手を出さないのも選択肢の一つです。
資金に余裕がない人
生活費や緊急資金の確保ができていない状態の人は、投資信託をやめておいたほうが無難です。
金融庁のデータでは、5年以内の運用で約10%の確率で元本割れするリスクがあるとされています。急にお金が必要になったときに、下落しているタイミングで解約すると損が確定します。
2020年のコロナショックで収入が不安定になった方の中には、すぐに現金が必要になり大きく値下がりしている投資信託をやむなく売却し、損失を被ったケースもあります。
まずは生活防衛資金をしっかり確保してから投資を始めるのが鉄則。余裕資金なしでの投資はリスクが高いので、注意が必要です。
株主優待を受けたい人
株主優待を楽しみに投資する場合、投資信託はまったく向いていません。
投資信託では、実際に株を保有しているのは信託銀行などであって、投資家自身は「間接的な出資者」の立場になります。そのため、優待は受けられない仕組みです。
外食チェーンや小売企業の株を直接買えば食事券や割引券がもらえる場合がありますが、同じ銘柄に投資する投資信託を買っても優待は得られません。
株主優待が目的なら、個別株の購入一択。投資信託を選んでも優待はないので検討対象から外してしまってもいいでしょう。
投資信託をやるのが向いている人の特徴

ここまで、投資信託を始めるのを勧めない人の特徴を見てきました。
それでは、逆に投資信託をやるのが向いている人の特徴について見ていきましょう。
投資の勉強を始めたばかりで資産運用の知識が少ない人
初心者でもプロの運用に任せられるので、投資信託は投資の第一歩としておすすめです。
金融庁の情報では、投資初心者がいきなり個別銘柄に手を出すより、分散された投資信託のほうがリスクが抑えられ、失敗も少なくなる傾向があるとのこと。
リーマンショックやコロナショックのような下落局面でも、複数の地域や資産に分散投資している投資信託であれば、特定のセクターに集中投資している場合より被害が少なかったという事例が報告されています。
知識が少ないうちは、プロに任せられる投資信託は心強い選択肢。まずは小額から始めるのが無理なく続けられるコツです。
リスクを抑えて投資を始めたい人
リスクを分散しやすい投資信託は、できるだけ安全に運用したい人に向いています。
投資信託は株式や債券、不動産など複数の資産をまとめて運用する仕組みが多く、金融庁の統計でも特定の一銘柄だけに集中するよりリスクが低減すると示されています。
2020年の市場急落時、個別株のみ保有していた人が一時的に大きく資産を減らした一方、バランス型投資信託を保有していた人はダメージを軽減できたケースが目立ちました。
「投資は怖いけどやってみたい」という場合は、投資信託でリスク分散しながらコツコツ始めるのが賢い方法です。
少額から投資をしたい人
投資信託は100円や1,000円などの少額からでもスタートできるため、初期費用を抑えたい人におすすめです。
日本国内の多くの投資信託では、小額積立に対応しており、金融庁のレポートによると毎月数千円単位から投資を始める人が増えているとされています。
毎月500円~1,000円を積み立てている社会人が、数十年後には数十万円~数百万円の資産を作れた事例も珍しくありません。小さな金額でも長い目で見れば大きな結果につながります。
「投資にはお金がかかる」というイメージは過去のものです。投資信託なら低額スタートでOKなので、初心者にもハードルが低いです。
投資に興味はあるけど時間がない人
普段忙しくて投資のチェックができない人ほど、投資信託はピッタリです。
プロのファンドマネージャーが運用方針に沿って銘柄を組み替えるため、投資家自身が頻繁に売買を判断する必要がありません。金融庁の調査でも、「自分は運用の手間をかけずに成果を得られるのが魅力」という投資信託ユーザーの声が紹介されています。
仕事で忙しいビジネスパーソンが、毎月の積立設定を一度行えば、あとは自動で買い付けが行われます。チャートを追いかける時間がなくても、長い目で資産が育っていく可能性があります。
時間に余裕がない人は、投資信託で自動積立を設定して“ほったらかし投資”を実践するのが得策です。
将来に向けた資産形成がしたい人
長期的にじっくり資産を増やしていきたい人にとって、投資信託は理想的な仕組みです。
20年以上の長期運用をした場合、元本割れリスクがほぼゼロになるというデータが金融庁から出ています。時間をかけることで市場の変動リスクを平準化できるわけです。
リーマンショック直後に積立を始めた人は、景気回復局面で基準価額が回復し、10年後には当初よりも大幅にプラスになったという報告が多数あります。
時間をかけてコツコツ積み立てるスタイルなら、投資信託のメリットを最大限に生かして将来の資産形成を狙えます。
投資について勉強していても、自分で銘柄を選ぶのが怖い人
知識はあるけど、実際に銘柄選定するのはちょっと怖い…という人には、投資信託が無難です。
日本証券業協会の調査では、個別株を運用している人の半数以上が「銘柄選定や売買のタイミングが難しい」と回答。投資信託ならその部分をファンドマネージャーに任せられます。
暴落局面や急騰局面で、人間は感情的になりがち。投資信託ならプロが淡々と運用してくれるので、狼狽売りやタイミングを逃すリスクが軽減されます。
ある程度勉強はしているけど、実践に踏み切れない人にとって、投資信託は安全策となり得ます。
投資信託を始める際の注意点

投資信託を始める際には、考えておくべき注意点が存在します。
ここでは、4つのポイントについてお伝えしていきます。
投資目的と目標金額の設定
明確なゴールがなければ、投資信託も継続しにくいので、まずは目的と目標金額をハッキリさせましょう。
金融庁の調査でも、具体的な目標設定をしている投資家ほど、運用成果に満足している割合が高いことがわかっています。ゴールが明確だと途中の下落局面でも売らずに持ち続けやすいからです。
例えば「老後資金2000万円を30年かけて貯める」という目標があれば、一時的に資産が下落しても粘り強く積立を継続しやすくなります。逆に目標が曖昧だと、すぐに損切りしてしまうケースが多いです。
投資信託を始める前に、「何のために」「どのくらいの期間で」「いくら貯めたいのか」をしっかり決めておきましょう。
運用実績の確認
投資信託を選ぶときは、必ず過去の運用実績をチェックすべきです。
金融庁のデータでは、過去のリーマンショックやコロナショックなどの大暴落を乗り越えてプラスを維持しているファンドは、下落耐性が高い傾向が見られます。
運用実績を軽視して購入した結果、いざ相場が荒れたときに予想以上の暴落に見舞われるケースがあります。一方、長期の成績が安定している投資信託は、急落時も比較的ダメージが少ないことが多いです。
短期的な成績だけでなく、5年・10年スパンで成績が出せているかをチェックする習慣をつけましょう。
リスクの把握
投資信託は元本保証ではないため、リスクを理解していないと想定外の損失を被る可能性があります。
株式型の投資信託は、市場環境によっては短期間で10%~20%程度の下落も普通にあり得ると、金融庁の報告で指摘されています。
リーマンショックやコロナショック時に、資産が一時的に半分以下になった投資信託も存在しました。事前にリスクを想定していないと、精神的負担が大きくなります。
「投資信託だから安全」とは限りません。きちんとリスクを理解した上で、自分の許容範囲かどうかを確認しましょう。
手数料の確認
投資信託の手数料は運用パフォーマンスに直結するので、事前のチェックを怠らないことが大切です。
信託報酬が1%違うだけで、20年後のリターンが数十万円以上変わる可能性があると、金融庁も注意喚起をしています。
毎年100万円を年率3%で20年間運用するとして、手数料が0.5%の商品と1.5%の商品では最終的な受取額に大きな差が出ることがシミュレーションで示されています。
長期投資なら、なるべく低コストの投資信託を選ぶのが得策です。
投資信託の活用方法

実際に、投資信託を活用していくために押さえておくポイントについて、見ていきましょう。
長期投資と積立投資の組み合わせ
長期間にわたって毎月コツコツ積み立てるやり方が、投資信託の王道スタイル。
金融庁の調査によると、20年以上の長期運用を行うと、短期的な暴落を吸収しやすくなり、元本割れリスクが大きく下がることがわかっています。
リーマンショックのような大きな下落局面でも、積立投資を続けた人は安い価格で多くの口数を買えたため、回復時に資産を大きく増やすことができました。
投資信託は「ほったらかしでコツコツ」が基本。長期×積立のコンボがもっとも効果を発揮します。
分散投資の実践
複数の資産クラスや地域に投資を分散することで、リスクを抑えられます。
金融庁のレポートでも、国内株式・海外株式・債券などを組み合わせると、特定の市場が不調でも他の市場の好調でカバーできる可能性が高まるとされています。
日本株だけに集中投資していた人は、国内景気が悪化すると大きな損失を抱えましたが、海外株式や債券も含む投資信託を保有していた人は損失を軽減できたケースが目立ちます。
分散投資は投資の基本。投資信託であれば自然に分散が効くものもあるので、積極的に活用しましょう。
税制優遇制度の活用
NISAやiDeCoなどの税制優遇を使うと、投資信託のリターンを大きく高められます。
NISAを使えば最大1,800万円までの元本に関して、運用益にかかる税金がすべて非課税になります。iDeCoなら掛け金が所得控除対象になるので、節税効果が期待できます。
例えば年利3%で10年運用した場合、非課税の恩恵があると数万円~数十万円の差が出る可能性があります。長期になるほどこの効果はさらに大きくなります。
投資信託をするなら、NISAやiDeCoを活用して税金面でもお得に運用するのが賢明です。
手数料の低い商品の選択
同じ運用成績なら、手数料が低いほど投資家の取り分は増えます。
信託報酬が1%違うだけで、長期的には最終的な資産額に大きな差が出ることは前述の金融庁の試算通りです。
アクティブファンドとインデックスファンドでは手数料が大きく異なる場合があります。インデックスファンドを選ぶだけで、運用パフォーマンスが同じなら手数料分の差が積み上がり、資産形成にプラスになります。
商品を選ぶときは必ず手数料を比較しましょう。特に長期投資では、この差が将来大きな額になって返ってきます。
定期的なリバランスの実施
ポートフォリオの比率を定期的に調整する「リバランス」は、リスク管理とリターン向上の両方に役立ちます。
金融庁の報告でも、リバランスを継続して行った投資家は、リスクが高まった状態を放置しなかったことで、長期的に安定したリターンを得られたというデータがあります。
株式が好調で比率が上がりすぎたら、一部を売却して債券などの資産を買い増す。これを怠った投資家は、暴落時に大きな損失を被ったケースが報告されています。
積立投資でも数カ月~1年に一度は資産配分を見直すことで、リスクを抑えながら運用効率を上げられます。
Q&A
- Q投資信託をやめたほうがいい理由は?
- A
投資信託をやめたほうがいいと考えられる理由はいくつかあります。
1. 元本割れのリスクがある
投資信託は短期間でも元本割れのリスクがあるため、資産が減る不安を感じやすい人には向いていません。特に市場の下落局面では基準価額が急激に下がることがあり、精神的な負担が大きくなります。2. 運用手数料がかかる
投資信託には信託報酬(運用手数料)がかかり、長期投資ではその負担が大きくなります。手数料が高いファンドを選ぶと、最終的なリターンが低くなる可能性があります。3. 短期間での利益獲得が難しい
投資信託は基本的に長期運用を前提としているため、短期間で大きな利益を出したい人には向いていません。短期的な市場変動の影響を受けやすく、安定したリターンを得るには時間が必要です。4. 商品選択の難しさ
投資信託の種類は非常に多く、最適な商品を選ぶのが難しいという問題があります。手数料が高いファンドやリスクが大きいファンドを選んでしまうと、思わぬ損失につながる可能性があります。
- Q投資信託をやるのが向いている人の特徴は?
- A
投資信託は特定の条件に当てはまる人にとっては有効な資産運用の手段となります。以下のような人には特におすすめです。
1. 投資の勉強を始めたばかりの人
投資の初心者でもプロの運用に任せられるため、資産運用の第一歩として適しています。投資信託なら分散投資が可能で、リスクを軽減しながら投資の経験を積めます。2. リスクを抑えて投資をしたい人
投資信託は複数の資産を組み合わせることでリスクを分散できる仕組みになっています。そのため、できるだけ安全に資産を運用したい人に向いています。3. 少額から投資を始めたい人
投資信託は100円や1,000円などの少額から投資できるため、初期費用を抑えて投資を始めることができます。特に積立投資を利用すれば、毎月の負担を少なくしながら資産を増やせます。4. 投資に興味があるが時間がない人
プロのファンドマネージャーが運用するため、頻繁にマーケットをチェックする必要がありません。ほったらかしでも資産を増やすことができます。仕事や家事が忙しく、投資に時間を割けない人に適しています。5. 将来に向けた資産形成をしたい人
長期的に資産を増やしたい人にとって、投資信託は効果的な手段です。特に20年以上の長期運用を行うことで、リスクを抑えながら資産を増やすことができる可能性があります。6. 銘柄選びに自信がない人
個別株の選択や売買のタイミングを判断するのが難しいと感じる人は、投資信託のほうが安心して運用を続けられるでしょう。プロが運用するため、個別銘柄の分析をする必要がありません。投資信託はすべての人に最適なわけではありませんが、上記の条件に当てはまる場合は有力な選択肢となるでしょう。
- Q投資信託を始める際の注意点は?
- A
投資信託を始める際には、以下のポイントを事前に確認することが重要です。
1. 投資目的と目標金額の設定
明確な目標がないと、運用中に迷いや不安が生じやすくなります。例えば「老後資金として30年間で2000万円を貯める」など、具体的なゴールを決めましょう。2. 運用実績の確認
過去の運用成績が安定している投資信託を選ぶことで、リスクを抑えることができます。特に暴落時にどのような動きをしたかを確認することが重要です。3. リスクの把握
投資信託は元本保証がないため、市場の影響で大きく値下がりすることもあります。短期的な価格変動に耐えられるかどうかを考慮しましょう。4. 手数料の確認
信託報酬や販売手数料が高すぎると、長期運用のリターンに悪影響を及ぼします。手数料の低いインデックスファンドなどを選ぶのが賢明です。投資信託は正しい選択をすれば有益な資産運用手段になりますが、事前の準備と注意が必要です。
- Qもし、始めた投資信託をやめるべきか迷ったときの判断基準は?
- A
投資信託を続けるかやめるか迷ったときは、以下のポイントをチェックして判断しましょう。
1. 投資目的が変わったかどうか
最初に設定した投資目的(老後資金の確保、教育資金の準備など)が変わった場合、投資信託が適しているか再評価しましょう。目的に合わなくなった場合は、解約や別の運用方法を検討するのが良いでしょう。2. 運用成績が期待と異なるか
長期間にわたって運用成績が低迷し、目標としていたリターンを得られていない場合は、他の投資手段に切り替えることも選択肢になります。ただし、短期的な価格変動に惑わされず、最低でも5年以上のスパンで評価することが重要です。3. 生活資金に影響を与えていないか
投資信託に回している資金が生活費や緊急資金に影響を与えていないか確認しましょう。万が一の出費に備えて十分な現金を確保していない場合は、投資を続ける前に資金計画を見直す必要があります。4. 価格変動にストレスを感じていないか
投資信託の価格変動に過度なストレスを感じる場合、精神的負担が大きくなる可能性があります。投資を続けること自体が心理的に負担になっている場合は、一部売却や投資手法の見直しを考えましょう。5. 手数料や税金の影響を考慮しているか
投資信託を解約すると、手数料や税金が発生する場合があります。短期間で売買を繰り返すとコストがかかり、利益を圧迫する可能性があるため、慎重に判断しましょう。これらのポイントを確認し、自分の状況に合っているかどうかを冷静に判断することが大切です。迷った場合は、一度立ち止まり、長期的な視点で見直してみるのも良いでしょう。
- Qもし、始めた投資信託をやめる際に相談すべき相手は?
- A
投資信託を解約するかどうか迷った場合、以下の専門家や機関に相談すると適切なアドバイスを得ることができます。
1. 証券会社・銀行の担当者
投資信託を購入した金融機関の担当者に相談することで、運用状況や解約のメリット・デメリットについて詳しく聞くことができます。ただし、手数料の関係で解約を引き止められる可能性もあるため、客観的に判断しましょう。2. 独立系ファイナンシャルプランナー(FP)
中立的な立場のファイナンシャルプランナー(FP)に相談することで、投資信託の運用だけでなく、ライフプラン全体を考慮したアドバイスを受けることができます。特にIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、特定の金融機関に属さないため、公平な視点でアドバイスをしてくれることが多いです。3. 税理士
投資信託を解約する際に発生する税金について詳しく知りたい場合は、税理士に相談すると適切なアドバイスを得られます。特にNISAやiDeCoの非課税制度を活用している場合は、解約による税負担を最小限に抑える方法を確認するのが重要です。4. 投資コミュニティや勉強会
投資に関する勉強会やオンラインコミュニティに参加し、他の投資家の意見を聞くのも一つの方法です。ただし、SNSなどの情報は玉石混交であるため、信頼できる情報を見極める力が必要です。5. 家族やパートナー
投資信託の解約が家計や将来設計に影響を与える場合、家族やパートナーと相談しておくことも大切です。特に、共同で資産を管理している場合は、将来の資産形成計画を共有しながら決定するのが望ましいです。投資信託をやめるかどうかの判断は、個人の状況によって異なります。専門家の意見を参考にしながら、自分にとって最適な選択をしましょう。
まとめ
それでは、この記事の内容についてまとめていきましょう。
- 投資信託は短期間では元本割れのリスクがあり、短期投資には不向き
- 運用手数料がかかり、長期運用ほど影響が大きくなる
- 商品選択が難しく、適切な投資信託を選ぶ知識が必要
- 短期間での利益を求める人や、自分で銘柄を選びたい人には不向き
- 投資信託は分散投資が可能で、長期運用には向いている
- NISAやiDeCoなどの税制優遇を活用するとお得に運用できる
- 投資信託を始めるなら、目的設定やリスク管理が重要
投資信託にはメリットもありますが、短期間での利益を狙う人や手数料負担が気になる人には向いていません。
自分の投資スタイルや目的に合った方法を選ぶことが大切です。
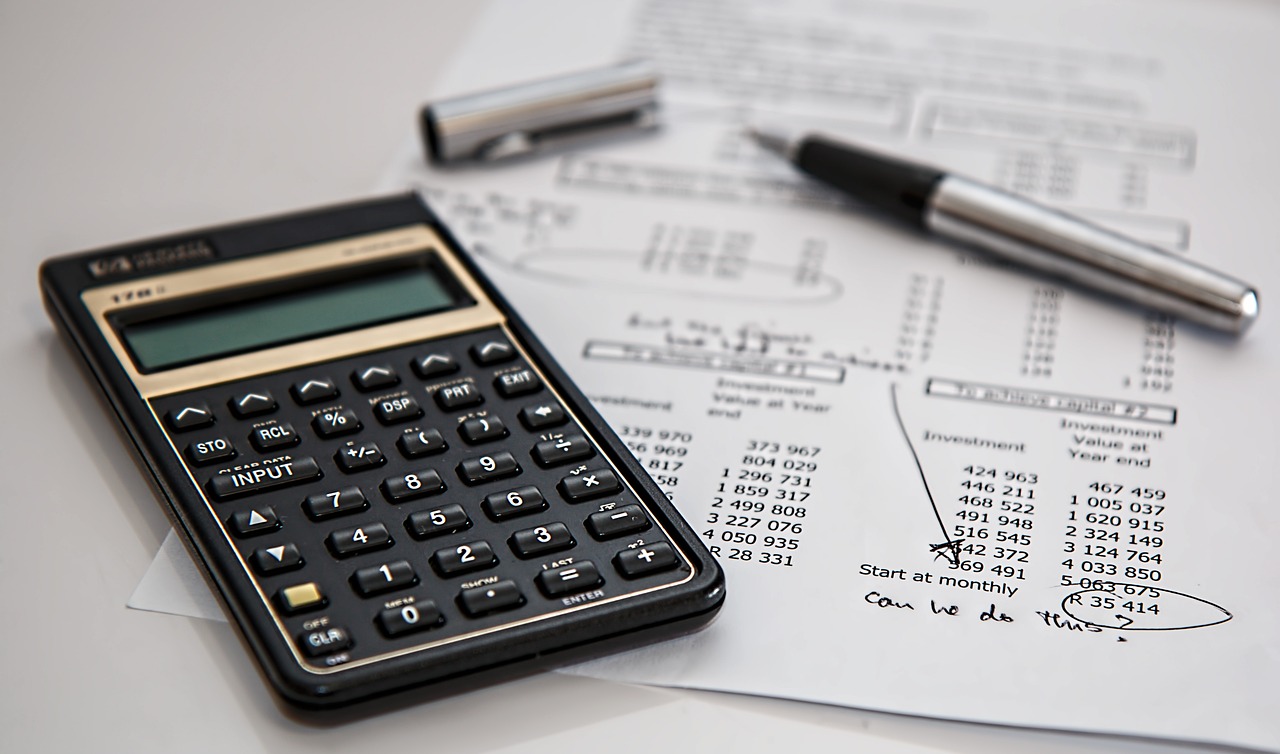
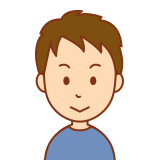

コメント